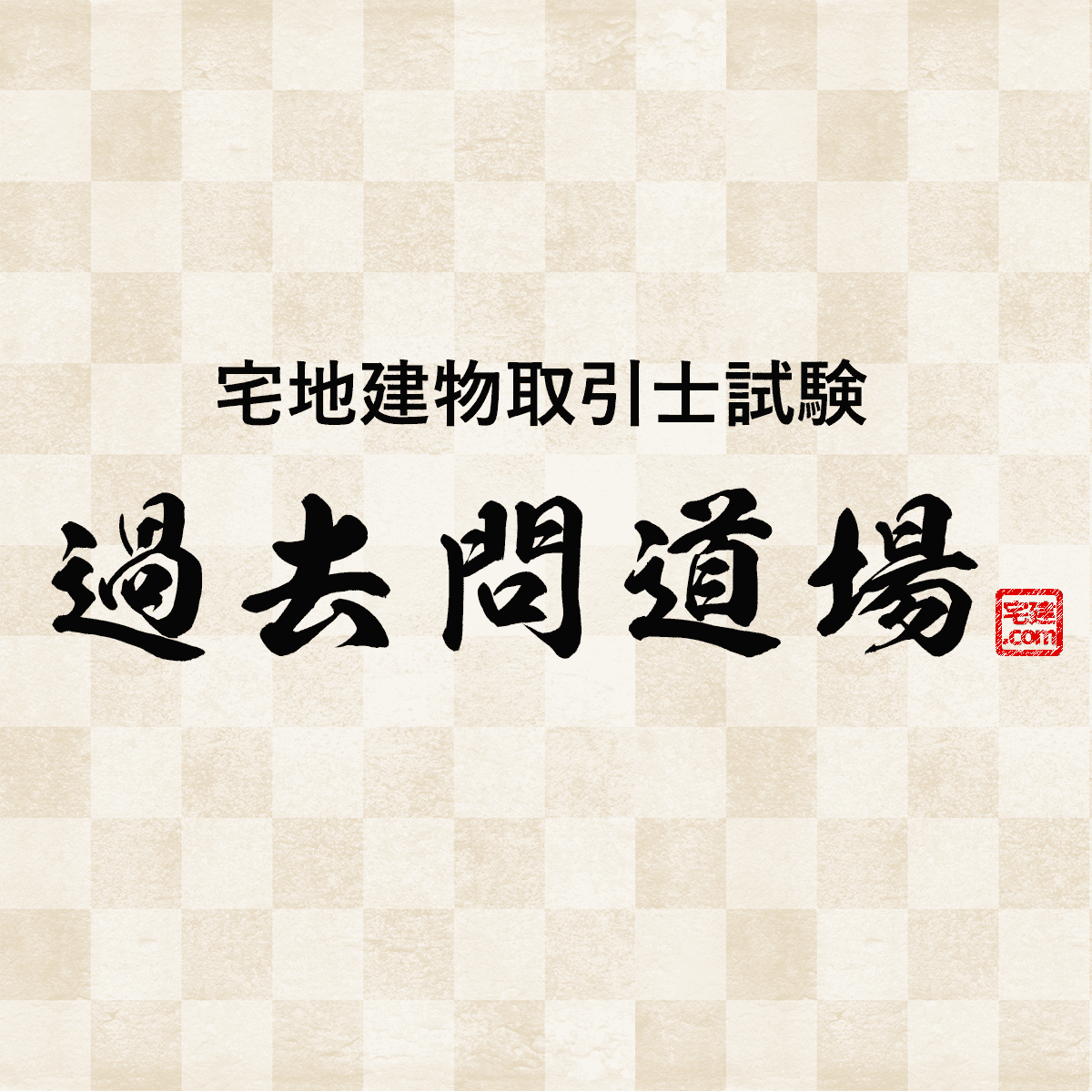- 大学生で宅建試験の勉強したい
- ボーダーより高得点で合格したい
- 短期間で合格した人の具体的なスケジュールを知りたい
このような方におすすめの記事です。
私のブログでは宅建試験合格者にインタビューをしています。
今回の記事の執筆者は大学生で独学で合格した人です。
ボーダー34点よりも8点高い42点でらくらく合格されました。
5ヵ月間という短期間で仕上げたみたいです。
この記事の執筆者
はじめまして、コケコッコーと申します。年齢は21歳(男)で、某大学の法学部に所属しております。私は就職活動を始める前に有利になる資格を取得したいと考え、勉強を始めることにしました。見事大学2年時に初回受験で合格することができました。合格当時の状況は、
- 10時から授業
- 休憩は空きコマで日によってバラバラ
- 17時から20時までアルバイト
といった1日のスケジュールでした。勉強を始めたのは受験年の令和3年5月の末でした。したがって、勉強期間は5ヶ月ほどです。私は42点で合格のため、比較的余裕がありました(ボーダーは34点)。

かかった勉強時間は450時間
学生だからこそ社会人に比べれば時間に余裕があるとはいえ、学校の課題やアルバイト、サークル等の学生ならではの予定もあったので、勉強時間の確保には人並みに苦労しました。おおよそ勉強時間は平日2時間・休日5時間程です。計450時間程度です。
一般的に、宅建の合格に必要な勉強時間は350時間と言われています。先に述べたように私は高得点での合格を目指していたので平均よりも多くの勉強時間を費やしました。しかし、「合格レベルに達するまで」の勉強時間で言えば、やはり平均の300〜350時間だったと感じています。
科目ごとの勉強時間は、民法2:宅建業法4:法令上の制限3:免除科目1の配分です。とにかく私が意識していたことは宅建業法を極めることです。私は「業法を制する者は宅建を制する」と思っているほどです。
他の受験生は民法に苦労することもあるようですが、私は法学部という特権もあり、それほど苦労をしなかったのは優位だったと思います。
しかしながら、他の科目で言えば、実務経験も一般知識も皆無だったのでイメージが膨らまないという苦労もありました。したがって、民法以外の科目には特に不安が残る状態だったと思います。
5月末〜7月中旬で勉強したこと
試験勉強を始めた5月末から7月中旬に使用した教材は、テキストとYouTubeの無料講座です。
まず、使用していた参考書は、「わかって合格る宅建士 基本テキスト(TAC出版)」です。このテキストは、文字と図の配分が自分に合っていて通読するにはベストでした。また、出題された年や改正内容が明記されている点は私にとって大きなポイントだったと思います。
なお、「みんなが欲しかった」シリーズに比べると文字の量が多いので肌に合わないと感じる方も多いとは思います。テキストに関しては、どの本を選んでも合格に必要な情報は入っていると私は考えます。ぜひ、安心して、ご自身に合ったテキストを探してみてください。
この期間はテキストを読んだところでさっぱり分からない部分も多くありましたが、とにかく読み進めていくことに注力していました。
以下の画像のように、足りない部分は自身で補足していき、自分なりの教科書を作成していきました。そのため、私はあえて1からノートを作るようなことはしませんでした。

そして、YouTube動画については、テキストを読んでも理解できないところを「吉野塾」や「ゆーき大学」の無料講座を視聴しながら理解を深めていきました。
どちらの先生も非常に分かりやすく、知識を体系的にまとめることができました。さらに動画の中で宅建の専門的な用語を噛み砕いてくれていることもあり、分かりやすい表現はテキストに書き込んでおくようにしておきました。これが復習するときに思い出す手助けになったと思います。このように前半期はインプット中心の学習を行うようにしていました。
合格して振り返ってみると、この期間から過去問に着手すれば良かったと反省しています。私は宅建の勉強において、過去問は解くものではなく、読むものだと感じました。そして、過去問を読んで理解できるようになると、飛躍的に実力が伸びると実感しています。
それに気づいたのは8月以降でしたが、今の私がもう一度勉強をするとなればまず先に過去問から取り掛かることは間違いありません。この時期からアウトプットを含めた学習をすべきでした。
7月末〜9月末までに勉強したこと
7月末から9月末までが後半期です。この期間に使用した教材はテキスト、YouTube動画に加えて過去問です。
まず、テキストは今まで同様の学習を進めました。テキストを通読していき、わからない部分はYouTube動画による無料解説を視聴して補完していきました。また、お風呂に入っているときや運転中などテキストを読むことができない時間に動画を流し、リスニングのような形で学習を進めていました。
ここでは、10日間を一つのタームとして、民法・宅建業法・法令上の制限・免除科目を回していきました。このように繰り返し学習することで知識が定着し、アップデートさせることができます。
他方、この時期からは過去問に力を入れていきました。使用した教材は、TAC出版の「みんなが欲しかった! 宅建士の12年過去問題集」です。この問題集は過去12年分の試験問題が科目別に収録されており、さらに最新年度の本試験が収録されています。また、改正された部分の問題は削除されており、法改正に関しても安心して学習を進めることができました。
なお、「過去問道場」というサイトがあり、過去問学習に関しては同サイトを活用することもお勧めします。改正内容にも対応しており、また分野や年度を限定することができるので非常に便利でした。何より無料で使える点が財布に優しいです。
この過去問を取り組むにあたってポイントは2つあります。
1つ目は、取り組む科目を限定することです。宅建士試験は大別して4科目(民法・宅建業法・法令上の制限・免除科目)ありますが、私は宅建業法と法令上の制限のみを解くようにしました。
過去問は膨大な量でありながら同じ問題が頻発する科目もあれば2度と出題されない問題が出題される科目もあります。後者の科目に時間をかけるのは時間が勿体ないと思います。
そこで私は、過去問から繰り返し出題される可能性の高い宅建業法と法令上の制限に絞って取り組むようにしました。宅建業法と法令上の制限の両科目は出題がパターン化されており、過去問にある情報量を固めることができれば、合格に必要な知識レベルには到達することが可能だといえます。
一方、民法や免除科目については、出題傾向にバラ付きがあるので過去問で知識を固めることよりもテキストベースで必要事項を抑えていく方が効率的だと思います。さらに年度別ではなく、分野ごとに分かれた問題集を活用することで問題形式になれることもできました。もちろん、全ての科目を解くにこしたことはありませんが決して得策とは言えません。
以下の画像は民法の問題集(TAC出版 わかって合格る宅建士 分野別過去問題集より)の抵当権の問題です。このように、図式化させることも1つポイントだと私は思っています。

2つ目は、解くことよりも読むことに重点を置くことです。私自身、過去問に合格に必要な情報は集約されてると思います。だからこそ、テキストよりも過去問を重点的に学習していくことが合格に辿り着くと考えています。
もちろん、時間がある方はまずは読むよりも、解いてみるのも良いでしょう。しかし、時間がない方は、過去問は1つの知識を習得することを目的として読むことをおすすめします。
先に述べたように、私は過去問を解かずに直ぐに解説を読んで答えとなるポイント事項を掴むようにしていました。そして、誤りのある選択肢に関しては文の中でどこが誤りなのかを問題文と解説文を照らし合わせながら明らかにし、そのひっかけられている部分をテキストに書き込むようにしていました。
たとえば、下記の画像のとおりです。選択肢ごとに検討をしているのが分かると思います。

以上のとおり膨大な情報量を持つ過去問を有効活用することで効率よく学習を進めることができました。テキストの文を読んでいるだけではなかなか理解が深まらない分野も過去問を通して実際にひっかかることで知識が定着していくことが感じ取れるはずです。寧ろ間違えた方が知識の定着に繋がる気がします。
加えて、もし時間的に余裕があるのであれば、ここで一度模試を解いてみても良いでしょう。自分自身が今どのレベルにいるのか、立ち位置を確認することができます。そのうえで、得意分野と苦手分野を把握し、苦手分野を改めて固めることができるようになります。今思えば、この時点で模試を解いても良かったと思います。
10月から勉強したこと
10月は主に2つの学習をベースに対策を行いました。なお、今までと同様にテキストとYouTube動画を使ったインプットも続けていましたが、ほぼ同様に学習をしていたため、ここでは割愛させていただきます。
1つ目が模試です。私が使用していた模試は「TAC出版 出る順宅建士 当たる!直前予想模試」です。ここでは、実際の試験時間よりも早く解く練習も同時に行っていました。全部で4個の模試を解きましたが、すべて1時間以内で解き終わっていました。
ここでポイントは解いた後に直ぐに解説を使って答え合わせをすることが重要です。解説を見る時はすべての問題ではなく、すべての選択肢を理解できるように学習を進めていきます。このようにすることで近年増加しつつある「正しいものはいくつあるか」という個数問題にも十分に対応できる力が養われるかと思います。
たとえば、以下の画像のとおり、「問1が合っていたから良かった」ではなく、「1つ1つの選択肢を理解しているか」という点を意識して取り組んでいるのが分かるかと思います。このように誤っている部分やポイントとなる部分を解きながらマークするようにしていました。

各社の予想模試は実際の試験よりもやや難しく作成されているのは明白なので、ご自身の実力を点数で測るのではなく、いくつの選択肢を理解できているかという視点で見ていくべきだと私は思います。
とくに、税制問題等は私自身難しく感じましたが、多くの模試を体験していたことで試験当日は慌てずに解くことができました。この点から、模試を解くことで試験当日の心理的安定性を保つための練習にもなると私は思いました。
2つ目が、宅建業法の12年分の過去問を改めて解くことです。問題数で言うと、各年20問×12年=240問です。さらに、240問×4択=960個の文を読み直すことです。やはり、宅建業法を極めれば確実に合格に近づきます。時間的に難しい方は、半分の480個分の選択肢を読めると良いと思います。
このようにしてみると多く感じるかもしれませんが、実際にやってみればそれほど苦には感じないと思います。他の科目は捨てていました。したがって、宅建試験対策全体を通して、過去問は、宅建業法2回、法令上の制限1回を解いた(読んだ)ことになります。
この時期は精神的にも身体的にも疲弊してきます。不安になるのは仕方ないことなので、とにかく試験に向けて踏ん張ること。これだけです。この2週間で結果は大きく変わります。私も10月に入ってから不安でしたが、振り返ってみれば残りの2週間頑張ったからこそ良い結果がついてきたと今でも思っています。
独学で苦労した点
私の場合は学生なので全ての分野で実務を経験しておらず、テキストに出てくる用語が毎回馴染みのないものでした。もっとも、宅建に出題される単語は専門的であり、学生問わず誰もが直面する苦労だと思います。
そこで私が行っていたのは、「実際に現場で使われている資料をネットで検索し、イメージを膨らませること」です。たとえば、登記の勉強をしているときに実際に登記書類を検索してみたり、宅建業法における免許の勉強をしているときに実際に免許書類を検索してみたり、頭の中で今何の勉強をしているのかを確認しながら行いました。
とは言っても、本来の勉強が最も大事です。イメージを膨らませる余り、受験対策が進まずにいては元も子もありません。勉強の休憩中にスマホで眺めてイメージを膨らませるのが効果的だと思います。実務を知ることで勉強も楽しくなり、より学習が捗るかと思います。ぜひ、勉強の息抜きとして調べてみてください!
宅建試験に合格したいけど、分厚いテキストを一人で消化するのは難しい、質問したいことがある、という方にはアガルートやフォーサイトの通信講座をおすすめします。
アガルートもフォーサイトも、独学の受験生よりも高い合格率を誇り、評判も非常に良いです。質の高い教材とサポート体制が整っており、合格への道をしっかりサポートしてくれます。
| 商品 | 特徴 | 価格 | リンク |
|---|---|---|---|
 ➡アガルートの詳細 | 合格率60.3% ※入門総合 学習サポーターに相談可能 月に1回のホームルーム 合格特典で全額返金 ※フルカリキュラムのみ | 入門総合カリキュラム 54,780円と71,280円 演習総合カリキュラム 69,800と107,800円 | アガルート公式HP |
 ➡フォーサイトの詳細 | 合格率76.1% コンパクトな講義で高速でインプット可 eラーニングが充実 評判の高いフルカラーテキスト | バリューセット1 59,800円 バリューセット2 64,800円 バリューセット3 69,800円 | フォーサイト公式HP |
当ブログでは宅建試験に独学で合格された方にインタビューをしています。ほかの合格体験記はこちらのカテゴリーページからご覧ください。